みかんジュースの販売数1年で20本からのスタート。 GFPで生のみかん15トン輸出まで成長|陽だまりファーム
2025年3月28日(金)

静岡県・浜松市の三ヶ日町でみかんの生産を行う陽だまりファーム。台湾、シンガポール、香港などアジア圏を中心に年間15トンの輸出を行っています。しかし、GFPに登録した時点では、生のみかんの売り方をまったく知らなかったのだとか。陽だまりファームの代表取締役である高橋博之さんに、GFPに登録した経緯や、輸出を始めたきっかけ、生の果実ならではの難しさなどを伺いました。
インタビューさせていただいた方

株式会社陽だまりファーム
代表取締役
高橋博之さん
20代後半にハードウェアエンジニアから転職。農家としては2代目。今後の目標は、農家と消費者の垣根をなくした「一緒に作り上げる農業」を形にしていくこと。
競争率の高い国内市場を経験し、海外に活路を見出した
Q.GFPに登録した時期と、当時の課題感について教えてください。

高橋博之さん
当社は早生みかん、青島みかんを年間で延べ150〜200トン生産しており、2015年から加工品の製造にも取り組んでいます。加工品の製造を始めた当初は国内市場での販売をメインに考えていましたが、2017年頃から間接輸出にも取り組み始めました。そのような中で農林水産省からのメールマガジンを通じてGFPのことを知ったんです。
当時、すでに加工品の輸出実績はありましたが、生の果実を輸出する方法がわかりませんでした。そのため、メールマガジンから迷わずGFPに登録。積極的にセミナーや商談会に参加した甲斐あって、2023年には世界にみかんを輸出できるようになりました。

Q.加工品で間接輸出に挑戦したのはなぜでしょうか?

高橋博之さん
実は、海外への輸出はまったく考えていませんでした。そもそも加工品を始めたのは、当時所属していた農業組合の規約が変更され、加工品の製造・販売が可能になったことがきっかけ。そのため、生のみかんの延長線のように捉えていたのですが、蓋を開けてみれば、加工品の国内市場は非常に競争が激しい市場でした。類似商品がひしめく中で新規参入は相手にされず、まったく売れない、小売店と取引してもらえない、通信販売は価格競争になっているという厳しい状況。みかんジュースは1年で20本しか売れませんでした。周りとは違う市場を開拓するしかないと思い、輸出に踏み切ったんです。
Q.現在、輸出している国・地域を教えてください。

高橋博之さん
みかんを台湾、シンガポール、香港に輸出しており、加工品はマレーシアとも取引があります。2024年は生産量150〜200トンのうち、15トンを輸出する予定です。また、新たな輸出国としてニュージーランド向けに、日本の検疫と輸出の手続きを進めています。来年のトラップ試験*で問題がなければ、晴れて輸出となりそうです。
*トラップ試験
柑橘類の生果実を輸出する際に、輸出先の国から課せられる検疫条件。誘引性の罠(トラップ)などを利用して、果肉に寄生するミカンバエの発生がないことを確かめます。ミカンバエは防除方法が確立されている害虫ですが、寄生された果実が積荷に紛れ込むと現地の柑橘園などに甚大な被害が出る恐れもあるため、世界で広く警戒されています。
SNSやクラウドサービスなど、柔軟なデジタル活用が海外展開のカギ
Q.輸出先はどのように決まったのでしょうか。

高橋博之さん
GFPサイトで国内の商社とつながり、輸出への取り組みを始めました。新型コロナウイルス感染症の流行と時期が重なっていたため、商談はほとんどオンラインです。現地に行ったのは香港のみでした。現地バイヤーとの商談は英語で行いますが、当社の場合は商社に入ってもらっているので、言語面で困ることはありませんでした。

輸出先とのつながりができたことで、海外で行われる展示会にも参加するようになりました。静岡県・浜松市は、香港、シンガポール、マレーシア、タイなどで「静岡フェア」「浜松フェア」などの展示会を行っており、当社の商品も展示ブースに並べられています。
Q.輸出を通じて気づいた日本との違いを教えてください。

高橋博之さん
海外では傷ひとつないきれいな見た目のみかんが求められる、というのは輸出で得られた気づきです。みかんの大きさに対する捉え方も文化によって異なり、日本を含むアジアは小玉のみかんを好む傾向にありますが、ニュージーランドでは大玉のみかんが好まれます。
また、購買に対する考え方や商習慣にも大きな違いがありますね。日本は人口減少などの理由から、みかんの市場が縮小してきていますが、海外はまだまだ盛ん。多くの国・地域は「良いものにはお金を払う」というスタンスなので、生産者が価格交渉しやすい風土があります。日本の4倍ほどの価格がつくこともあるんですよ。
Q.海外のお客さまを獲得するために、どのような取り組みを行いましたか。

高橋博之さん
SNSでの定期的な情報発信が効果的でした。若い世代を呼び込むのであれば、今はショート動画がおすすめ。当社がSNSでアップした動画の閲覧ボリュームなどを分析してみると、ショート動画は若い人を中心に、海外からのアクセスがかなり増えています。名前を知ってもらうための第一歩として、ショート動画は影響力を増しているのではないでしょうか。
反対に長い動画を見ているのは年齢層が高めの方が多いです。そういったお客さま向けには、自社のことをもっと詳しく知っていただくために、英語のホームページを準備したのが良かったと思います。
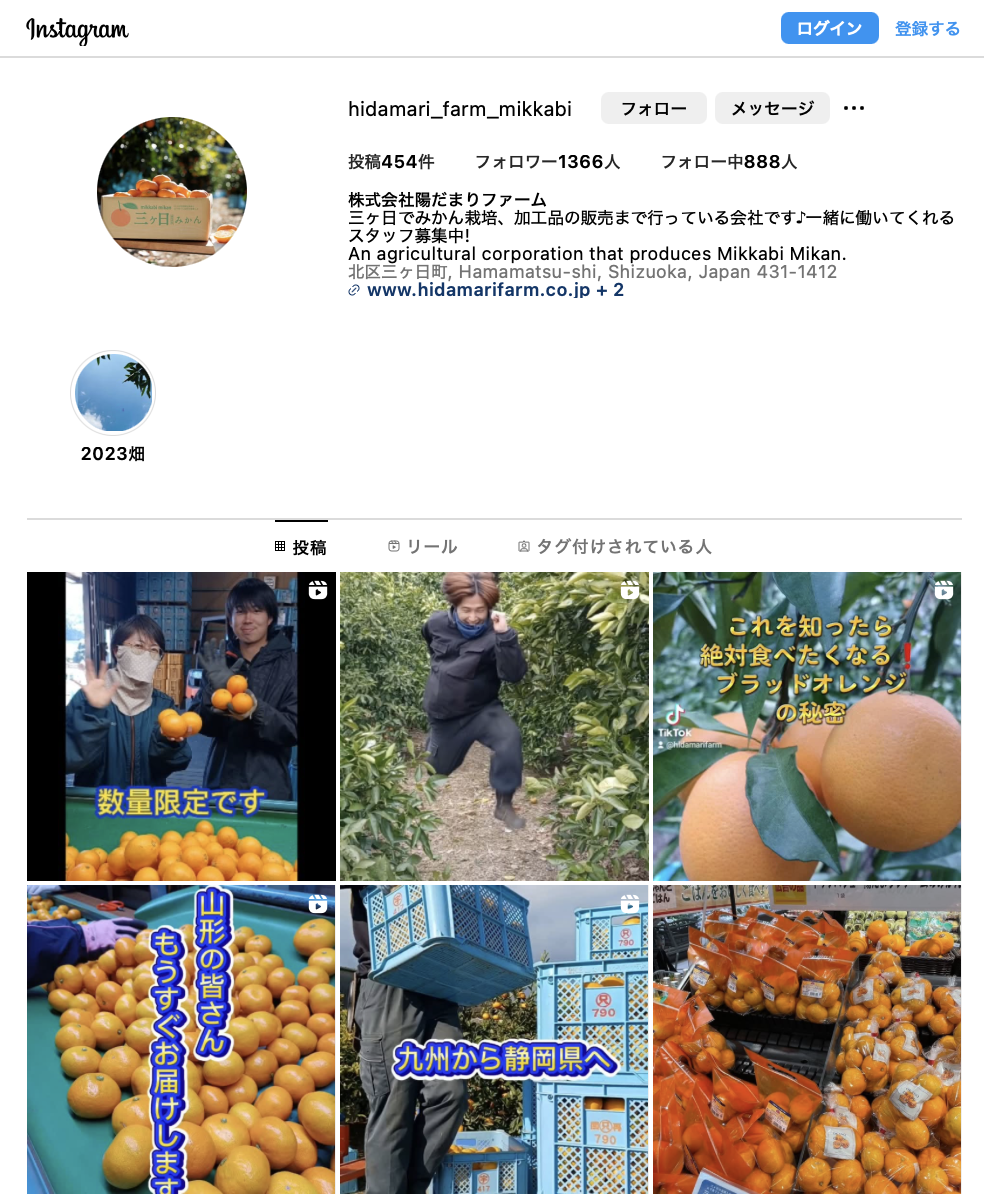
Q.輸出に関して苦労されたことを教えてください。

高橋博之さん
生鮮品なので、傷み・腐り・虫には入念に気を払っています。農薬検査はもちろん、国によってはさらに上の水準を求められます。たとえば、台湾はカイガラムシという害虫が1匹紛れ込んでいるだけで燻蒸されたり、廃棄されたりします。ニュージーランドはトラップ検査を2週間に1度行います。タイ、ベトナムのように現地の検査員が日本に来て、畑や選果場を直接検査する場合も。管理項目は多岐にわたりますので、当社では日報・防除履歴・トレーサビリティなどのさまざまな情報をクラウドで一元管理しています。

全体的な傾向としてデジタル活用が遅れている業界ですが、輸出に携わる上では導入しておいた方が便利ですね。規制が厳しい国に対しては、輸出専用の畑を作る場合もあるため、アナログだと管理しきれなくなってきます。輸出先に防除履歴・トレーサビリティの証拠を求められた場合に、そのままデータとして提出できるのも大きなメリットです。
課題は国内の人気ブランドと海外で競い合う仕組みづくり
Q.今後の輸出事業における目標を教えてください。

高橋博之さん
輸出が占める販売比率を50%まで高めることが目標です。実現に向けては国内みかんの人気ブランドとも競っていく必要があり、今はそのための戦略を練っています。実際のところ、香港やシンガポールでも日本の愛媛、和歌山のみかんは人気なんです。みかんが旬を迎える10〜12月は愛媛、和歌山産が大量に買われていき、年明けのみかんが無くなってきたタイミングで静岡の三ヶ日みかんにお呼びがかかるという流れが出来上がっています。その流れを打破して、海外でも初めから静岡のみかんが売れる仕組みづくりが課題です。「三ヶ日」という産地のブランディングをしていかなければと思っています。

Q.目標達成に向けて、GFPに期待されていることはありますか。

高橋博之さん
先ほど挙げた課題とは少し視点が異なりますが、輸出が難しい国・地域や、日本からの輸出事例がない国・地域にもアプローチできるとうれしいですね。香港、シンガポールへの輸出は規制や求められる品質が日本の環境に近く、国内向けに栽培したみかんをそのまま出せます。しかし、それは裏を返せば、競争率が高いということ。価格競争になったとき、私たちのような小規模生産者が、正攻法で一大ブランドと競うのは困難です。そのため、規制の厳しい国・地域には、かえって大きな商機が眠っていると思っています。
Q.これから輸出を始められる生産者の方にメッセージをお願いします。

高橋博之さん
まず、やってみる。この精神が大事。事業の安定性を考える上でも、さまざまな国・地域に販売チャネルを持っているというのは大きなアドバンテージになります。輸出に興味を持って、まずはとにかく挑戦することですね。



